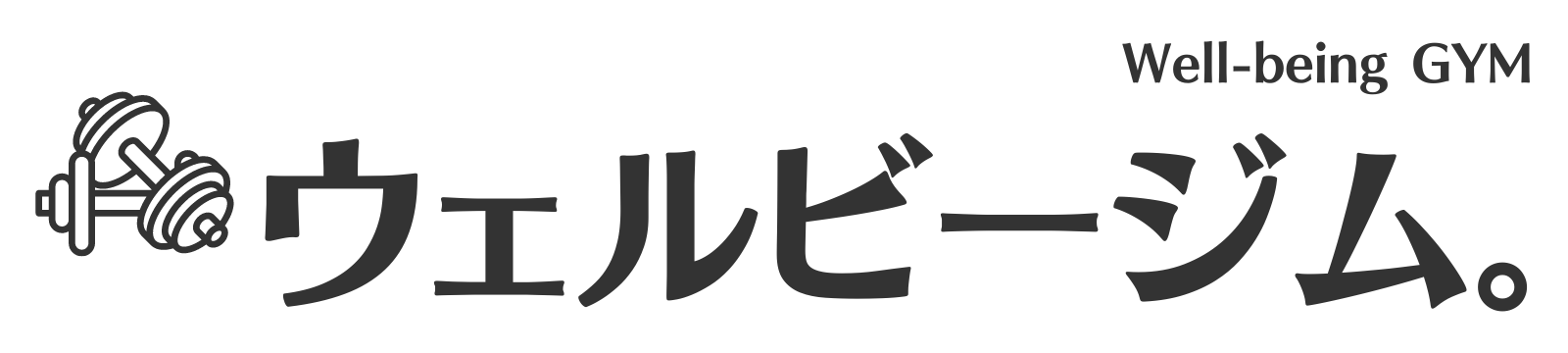ウェイトトレーニング~スクワット動作×加速度の重要性

目次
🔍 テーマ案:スクワット動作 3つの重要な関節動作と行動変容の変化
ウェイトトレーニング代表=スクワット動作=
3つの重要な関節運動を正しく行うことが最も大切です!!
1)足首の関節(足関節) 2)膝関節 3)股関節
正しくスクワットをするには、関節動作を理解していないとトレーニングをすることでその他のケガを誘発します!
例えば、
スクワットで膝が前に出る ⇒⇒⇒ 足首の関節可動域 問題
スクワットで身体が前傾する ⇒⇒⇒ 足関節、股関節から腰部の可動性
スクワットで腰が反る ⇒⇒⇒ 足首関節、股関節の使い方
と、足首の関節の関りが大きいです。
足首関節の関りを工夫しないで、無理に行うと腰椎症、膝関節に問題が出る可能性が大きいです。
🔑 ゆっくりスクワットする?本当にこれ正しいの?
1. スクワットのスピード・加速度
- 内容:スクワット動作における「立ち上がる速さ」や「下げるときの加速度」などの運動指標。
- 意義:立ち上がりが重要、無理に深く下がる動作は必要ありません
- 応用:筋力だけでなく、動作の「質」や「瞬発力」を応用動作に行う
2. 足腰の筋力(下肢筋力)
- 内容:大腿四頭筋や、ハムストリングス臀筋群など、歩行や立ち上がり動作に関わる筋肉。
- 関係性:スクワット動作のスピードや加速度は、足腰の筋力に比例しやすい。
- 測定:握力や下肢筋力測定(椅子立ち上がりテスト)などと比較できる。
3. フレイル予防
- 内容:加齢に伴う虚弱(身体的・精神的・社会的)を予防・遅延させる取り組み。
- 関係性:
- スクワットスピードの低下 → 下肢機能低下の兆候。
- 歩行速度の低下や活動量低下もフレイル指標。
- 応用:スクワットスピードを早期評価指標に使い、フレイル予防へつなげる。
4. 歩行速度
- 内容:加齢による運動機能低下の客観的指標。
- 関係性:
- 下肢筋力と連動。
- スクワット速度と歩行速度に相関がある可能性(研究例あり)。
5. 行動変容
- 内容:運動習慣の定着や、健康行動の継続的な改善。
- 理論例:
- トランスセオレティカルモデル(TTM:行動変容ステージ理論)
- 自己効力感の向上による行動維持
- 関係性:
- スクワットの測定結果を「見える化」し、モチベーション向上。
- 小さな成功体験が継続的な運動習慣に。
🎯 活用例
● 椅子の立ち上がりの不安、階段を降りるときの膝の痛み
- スクワット動作(立ち上がりがスムーズにできるか?)の効果測定
- 歩行速度や椅子立ち上がりテストと併用し、機能評価
- 関節の可動域改善と加速度を意識したスクワット動作
● フレイル予防
- 「スクワット動作の加速度は歩行速度および下肢筋力と相関し、フレイル予防の指標となり得る」
- 「スクワットのスピードフィードバックは行動変容を促進する効果がある」
🧪 研究デザイン例(簡易)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | スクワット加速度と歩行速度の関連性を調査 |
| 対象 | 高齢者30名 |
| 測定項目 | スクワット加速度、歩行速度、下肢筋力 |
| 方法 | 加速度センサーでスクワット動作を分析 |
| 解析 | 相関分析、重回帰分析 |
| 介入(任意) | フィードバック型運動指導(行動変容支援) |
📝 まとめ~正しいスクワット動作で、フレイル予防、歩行動作の改善~
身近なウェイトトレーニング”スクワット”を正しく行うことが重要。
ゆっくり行うという初期動作から、加速度を意識して行う。
40代頃から症状として見受けられる、立ち上がりの不安、歩くことへの不安、体力の不安は
多くの筋力、骨格が占める、下肢の筋力トレーニングが重要。
機能評価を行い、スクワットの効果を考察することが重要となります。